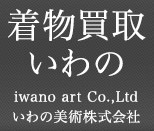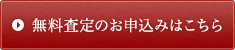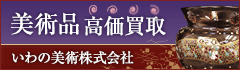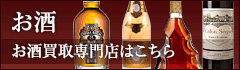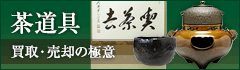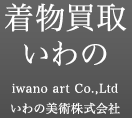かんざしとは
かんざしとは
かんざしとは~かんざしの由来
かんざし(簪)とは、女性が髪を結う時に使う日本の伝統的な髪飾りです。
現代のかんざしとは、お洒落な髪飾りというイメージがありますが、日本でのかんざしの歴史は古く、縄文時代にまで遡ることができるといわれています。
かんざしの語源は、「髪挿し(かみざし)」といわれ、髪飾りというよりも、呪術的な意味合いから、一本の細い棒を髪に挿すことで、魔を払うことができると考えていたようです。
奈良時代には、中国(唐)から様々な文化がもたらされ、その中に櫛の原型である挽き櫛や、二本足の釵子などの髪飾りが伝わってきました。
それらの髪飾りを漢語が「簪」と書かれ、「かんざし」というカナ読みが当てられました。 平安時代になると、髪を束ねずに下ろす垂髪が主流となり、国風様式に押されてかんざしなどの髪飾りは必要性がなくなり廃れてしまいます。
かんざしとは~かんざしの隆盛
江戸時代に入ると、「島田髷」「勝山髷」など、技巧を凝らした結髪が登場し、それに伴い、かんざしも再び用いられるようになりました。
江戸時代初期には、現在舞妓さんが愛用する京都で花びらを意匠とした「花びらかんざし」がつくられ、それが江戸に渡り「つまみかんざし」が発祥しました。
江戸時代中期以降、髪形が複雑化・大衆化するにつれ、かんざしは櫛や笄とともに必需品となり、江戸時代末期に最大の隆盛をみせ、平打ちかんざし、玉かんざし、花かんざしなど、髪飾り専門の職人が技を凝らした様々なかんざしがつくられました。
明治時代には、洋風化の流行とともにかんざしは衰え、今日では、神前結婚式での花嫁や、芸者・芸妓が日本髪を結う際に用いられるのが主な用途となりました。
最近では、和の美であるかんざしを普段の洋服にあわせて、ヘアアクセサリーとしてファッションを楽しむなど、密かに脚光を浴びつつあります。
かんざしとは~かんざしの種類
時代や髪形の変化に応じて、様々なかんざしがつくられてきました。
主なかんざしの種類には、以下のようなものがあります。
●玉かんざし...最もポピュラーなかんざしで、耳かきのついたかんざしに玉を1つ挿してあるだけのシンプルなものを指します。飾り玉には珊瑚、瑪瑙、ヒスイ、鼈甲、象牙、ギヤマンなど様々なものが用いられます。
●チリカン...芸者などが前差として用いる金属製のかんざしで、飾がゆらゆらと揺れて触れ合い、ちりちりと音を立てることからこの名がつきました。
●ビラカン...頭の部分が扇形や丸い形をしたかんざしで、家紋が捺されています。現代の舞妓がビラカンを前挿しにして使います。ビラカンは、舞妓だけで芸妓になったら使用しません。
●つまみかんざし...小さい絹の布を折りたたんだものを、幾重にも重ねた江戸のかんざし。江戸時代は土産物として人気が高かったそうです。
花をモチーフにしたものは「花かんざし」といわれ、現代では舞妓やこどもの七五三の髪飾りとして使われます。
季節によって付ける細工が決まっているのが花かんざしの特徴で、例えば、正月は稲穂、一月は寒菊に松、鶴、二月は梅、三月は菜の花….と季節感を楽しむことができます。
他には、鹿の子留、位置留、吉丁など様々なかんざしがあります。トンボ玉などを使った玉かんざしを、洋服にあわせて、さりげなく結った髪に使うのも、現代の粋なお洒落の楽しみ方かもしれません。