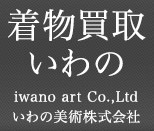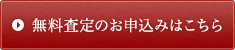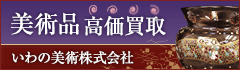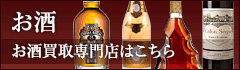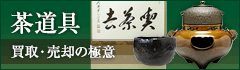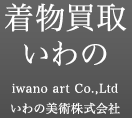和装コラム~着物コーディネート(秋)
暑さの厳しい夏が終わると、木々の紅葉が美しい秋になります。
秋は涼しい季節というイメージがありますが、日によって残暑が続いていたり、はたまた冬のような寒さになったりと忙しい季節でもあります。
今回も、秋に着る文様や、着物のコーディネートについてお話致します。
秋に合う着物の文様
夏に着る着物は、水色や白などの涼を取り入れた色合いが多かったですが、秋は逆に深みのある色を着て、暖かみを演出させるのが上級者コーディネートとなります。
紅葉
春と言えば桜、夏と言えば向日葵というように、秋の代表的な木として紅葉が有名です。
紅葉は、楓の葉が枯れる前に緑から黄色、赤へ変わった葉の事を指し、日本の秋の風物詩とも言われています。
また、日本のみならずアメリカやフランス、中国などでも見られる事から、今では世界の秋の風物詩ともされています。
楓の葉は、その形が蛙の手に似ているので蛙手と呼ばれていますが、蛙は語呂合わせで還るに通じ、還という字は60年生きて再び元の干支に還るという意味の還暦にも使われる事から、楓は長寿を表す文字とされています。
また、緑から黄色、赤、茶色など様々な色に変化して季節ごとに人々を楽しませる事から世渡り上手とも言われ、縁起の良い文様として数多く用いられています。
紅葉が描かれた着物は、とても華やかなので帯は黒や金色のシンプルなものを着用するといいでしょう。
その他にも、紅葉柄の着物に紅葉柄の帯を重ねる事で上級者コーディネートにもなります。
ススキ
お月見でお団子と一緒にお供えするススキは、穂の部分がフワフワしていて馬などのしっぽに見える事から尾花とも呼ばれ、秋の七草の1つと言われています。
日本では、万葉集が多く書かれていたとされる西暦660年頃から愛されていたそうで、万葉集の中では尾花やはた薄と明記されていたそうです。
古くから愛されているススキは、茎の中が空洞になっているのですがその空洞の部分に神が宿るとされ、神の依り代とも考えられていました。
また、ススキを切った時に出来る切り口が鋭利な刃物の刃先に見え魔除けになるという事で、現在でもお月見で使ったススキを捨てずに玄関先や庭に飾っている地域もあるそうです。
ススキが描かれた着物は、グレーや紫などシックな色合いが多く大人な女性を感じさせるお品物になっています。
この着物には、明るい色の帯を付ける事で全体を引き締めると美しいコーディネートに仕上がります。
桔梗
その凛とした美しさから、「気品」「清楚」「従順」という花言葉が付けられた桔梗は、秋の七草にも選ばれている歴史ある花で、根の部分は漢方としても利用されていました。
日本女性のような和の気品を持ち端正な姿、紫の色がとても美しく、昔から着物や帯の文様に数多く用いられています。
気品を持つ桔梗ですが、蕾の時風船のように膨らむ事から海外ではバルーンフラワーと呼ばれ、蕾が開くと星形の花びらが見られる可愛らしい一面も特徴となっています。
桔梗文様の入った着物は、着るだけで気品ある上品な大人を演出出来ます。
帯はシンプルなデザインを身に着け、周りに差を付ける大人コーディネートに仕上げましょう。
撫子
撫子は、とても小さく可愛らしい花で、「撫でたくなるような可愛い子」という意味で撫で子から撫子という名前がつきました。
中国から平安時代の日本に伝わった撫子は、その可愛らしさから日本の秋の七草にも選ばれ、源氏物語や枕草子にも登場し、鎌倉時代には調度品や着物に撫子文様が描かれるなど古くから愛されている花です。
よく日本人女性の事を大和撫子と呼びますが、これは撫子の花が清楚で控えめなのに凛とした姿がまるで日本人女性のようだという意味で呼ばれるようになった言葉です。
撫子文様の着物は、撫子の細かい花が着物いっぱいに描かれている作品ですと華やかな印象を与え、袖や裾部分などポイント的に撫子文様が描かれている作品は上品さを感じさせます。
華やかな着物には金や黒で引き締めたり、逆に着物と同じような華やかな帯を身に着けるのもいいかと思います。
山茶花
「さざんか さざんか 咲いた道~」という歌詞でお馴染みのたき火という童謡の歌に出てくる山茶花は、日本原産のツバキ科の植物です。
山茶花は椿と形が似ている事から、中国語で椿の花という意味の山茶花という漢字があてられました。
山茶花と椿は、見た目がとても似ていますので造園屋さんでも間違える事が多いそうです。しかし、葉の形、派の裏の毛、花の大きさや形など異なる点はありますので、そこが見極めるポイントになります。
また、椿の花が散る時は花首から落ちるので武士などから「首が落ちる」と言われ縁起の悪い花と嫌われていますが、山茶花が散る時は花びらが落ちるのでこちらの方が縁起の良い花になります。
椿の「首が落ちる」というイメージが嫌な方は、椿に似た山茶花文様の着物がオススメです。
赤やピンクなどの華やかな色には金や黒などの帯、紫やグレーのシックな色には白や淡い紫など優しい色の帯を身に着けると良いでしょう。
秋に着る着物
秋は夏と冬の間にある季節ですので、9月初めの頃は残暑が続いたり、10月には一気に寒くなったりと、気候の変化が激しい季節でもあり、朝と夜で気温の差が激しくなったりもします。
まだ残暑が続いていて暑い時には、裏地のない単衣の着物を着る事で風通しがよく暑さの続く残暑でも乗り切る事が出来ます。
そして、10月に入り寒くなってきた時には裏地の付いている袷の着物を着ましょう。
袷の着物は裏地が付いていますので、風が通るのを防ぐので寒さが緩和され暖かく過ごせますが、袷の着物だけで寒い場合は、羽織などを着用する事で防寒対策が出来ます。
着物の買取について
いわの美術では、ご不用になった着物や帯、和装小物などをお買取りしております。
ご自身で着ていた着物、お母様やお婆様が着ていた着物などご不用になり処分をお考えでしたら、一度いわの美術までご相談ください。
また、着物の売却の際には、証紙を呼ばれる着物の保証書のような布切れがありますと評価が上がりますので、一緒にお持ちの場合は処分しないようお願い致します。
ご売却をお考えの着物や帯がご自身のではなく作家や織元がわからない場合は、お品物のお写真をお撮り頂き、LINE、メールにて画像を頂けますと査定額をお伝えする事が可能ですので是非ご利用ください。
いわの美術では、着物以外にも様々なお品物をお買取りしております。
主な例としましては、お茶道具、掛軸、絵画、日本刀、甲冑、勲章、洋食器、ガラス工芸、中国美術、仏像、洋酒など他にも様々なお品物をお取扱いしております。
コレクションの整理、引っ越し、遺品整理、蔵の整理、家の解体、生前整理などで処分をお考えのお品物がございましたらいわの美術までお気軽にご相談下さい。