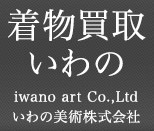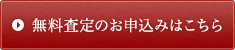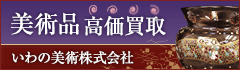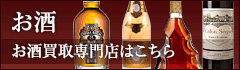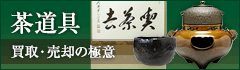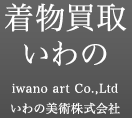夏のきもの生地
夏のきもの生地
夏の着物に用いられる生地には、様々なバリエーションがあります。それぞれの生地の特徴を知ることによって、着用時期や夏のきものの楽しみ方を広げることもできます。
ここでは夏きものに使われる代表的な生地を紹介します。
紋意匠縮緬(もんいしょうちりめん)
紋意匠縮緬は、緯糸を二重に織り出し、光沢のある地紋がはっきりと浮き出てみえる緯二重織縮緬ですが、夏用の紋意匠縮緬の生地は、その中でも肌にさらりとするように布面に細かい縦シワを出した楊柳のものが用いられます。単衣のきものの代表的な生地です。
本塩沢(ほんしおざわ)
新潟の塩沢地方で織られる御召織物で、細いシボが特徴の絹織物です。さらりとした肌ざわりと、十字絣と亀甲絣により構成された柄が上品な印象で、単衣にも好まれますが、袷としても用いられます。
夏塩沢(なつしおさわ)
本塩沢の盛夏版で、明治時代に改良されて生まれた、薄手で透け感のある絹織物です。小絣も人気です。
絽/三本絽(ろ/さんぼんろ)
平織に横段で絽目を表し、平織部分の緯糸の三本ごとに絽目を入れた生地で、透け感が最も強く、盛夏向きの生地です。
絽/九本絽(ろ/きゅうほんろ)
三本絽と構造は同じで、緯糸九本ごとに絽目が入ったものです。三本絽より透け感が少なく、現在では主に盛夏に用いられます。
乱絽(らんろ)
三本絽や九本絽のように規則的に絽目が入るのではなく、ランダムに調整された生地です。格子などの変わり絽目のものもあります。
竪絽(たてろ)
竪に絽目を通した生地で、普通の絽よりも透け感が少なく、現在は盛夏に主に用いられる傾向にあります。
絽縮緬(ろちりめん)
シボ立ちの細かい縮緬地に絽目を通したものです。かつては単衣向きとされていたそうですが、現在は夏中を通して着用されています。
上布(じょうふ)
芋麻やラミーなどの麻糸を用いて織る、上質な麻織物です。宮古上布、八重山上布、越後上布など産地により様々な種類があります。
麻縮(あさちぢみ)
強い撚りを掛けた麻糸を使って、布面にシボを表した麻織物で、小千谷縮が代表的です。爽やかでさらりとした肌触りが特徴です。
夏御召(なつおめし)
夏向きに織られた薄手の御召で、薄御召ともいいます。絹糸織物でシボがあり、さらりとした地風です。
紗(しゃ)
二本の経糸を一本の緯糸にからませるところから捩り織ともいわれる織物です。通気性に富み、清涼感があることから、盛夏用の訪問着や小紋の染下地などに用いられます。
紋紗(もんしゃ)
捩り織りで隙間を織り表した紗の中でも、地紋を織り出したタイプです。盛夏に主に用いられます。
夏大島(なつおおしま)
盛夏向きの大島紬で、薄く透け感のある絹織物です。強撚糸を用いているため、ごく細かなシボ立ちがあり、シャリ感があります。
琉球上布(りゅうきゅうじょうふ)
沖縄で織られる透ける絹織物で、しゃり感と沖縄らしい絣が特徴です。上布のように軽いのでこの名がつきました。