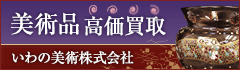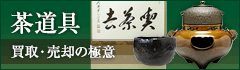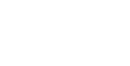- TOP >
- 新着情報 >
- 関東地方の染織品~黄八丈
関東地方の染織品~黄八丈
関東地方の染織品~黄八丈
黄八丈の歴史
鮮やかな山吹色の黄八丈(きはちじょう)は、東京から約290キロ南に位置する八丈島特産の絹織物です。
島に自生する植物の煮汁で黄色、樺色、黒に染められた糸を用いて、粋な縦縞や格子縞模様に織りあげたもので、現在は伝統的工芸品として国の指定を受けています。
八丈島の織物の歴史は古く、平安時代には絹織物が織られていたといわれています。八丈島は、かつて桑の木が自生し養蚕が盛んに行われていました。八丈島の繭は病気も少なく、本土の勢力がこの良質な絹織物に目をつけ、鎌倉時代には執権北条氏に黄紬が献上されたとの記録があり、室町時代には関東管領上杉氏、北条氏、奥山氏、三浦氏が八丈島の絹織物を求めて争ったといいます。
八丈島の「八丈」という名は、もともと一疋(二反分)の長さを曲尺で八丈(約24m)に織り上げた絹織物の呼び方に由来します。江戸時代の国学者・本居宣長が「八丈という島の名はかの八丈絹より出ずるらむかし」と書き残しています。
八丈の絹は15世紀頃から貢納品として本土にわたり、徳川幕府の直轄地になると、稲作に向かなかった八丈島の年貢として納められるようになりました。
八丈島は古くから都からの流人の地として知られますが、その都落ちした流人らによって、優れた絹織物の技術がもたらされました。
江戸時代前期・寛永年間にはマダミの樹皮を使った織物が織られるようになり、江戸時代中期・寛政年間頃に現在の黄八丈に使われる染色技術が完成されたといわれています。
江戸時代には黄八丈の美しい色艶が尊ばれ、武家やその子女、奥女中などが愛好し、やがて町人にも広がりをみせます。
「恋娘昔八丈」という人形浄瑠璃が安永4年(1775年)に上演され、翌年に歌舞伎として上演されますが、瀬川菊之丞がお駒役で黄八丈を着用し、その余りにも鮮やかな色が大評判となり、これをきっかけとして黄八丈が江戸で大流行となりました。
現代にも通用する粋な縦縞、格子縞が織られるようになったのは、江戸時代の中期以後からとされています。
黄八丈ができるまで
黄八丈の染材は、八丈島に自生する3種の植物です。色鮮やかな山吹色は小鮒草(イネ科の一年草)、樺色(茶系)はマダミ(たぶの木)、黒は椎で染められています。
縞・格子だけの黄八丈は、色がもっとも大切な要素となり、染材となる植物は、種まきなどの栽培や採集に始まり、染液をつくっては染め、乾かすことを数十回繰り返します。染液は一度使ったら捨て、常に新しい染液を造ります。 鮮やかな山吹色の黄染に用いる灰汁の灰は真夏に2日がかりで椿と榊を燃やしてつくり、黒染は全国でも珍しい泥媒染を行います。このような伝統的な手法によって、手間と時間を掛けて、輝くような黄色と、深みのある樺色、漆黒の黒の糸が染め上げられるのです。
糸が染め上ったら、糊付け、粋巻き、整経などの機織りの準備を経て、高機で織ります。黄八丈の模様は縞、格子だけですが、平織りだけでなく、多くの綾織りの技法があり、色と島、格子、綾織りの地紋の組合せ方で様々な表情が生れます。
天然素材を用いて時間と手間をかけて生まれた黄八丈という絹織物は、強固な染めと織で、孫や曾孫の代まで色褪せないといわれています。