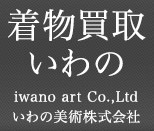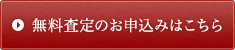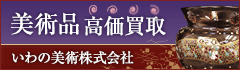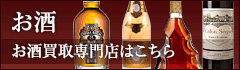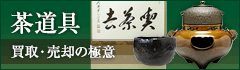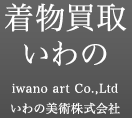- TOP >
- 新着情報 >
- 和装小物の選び方~帯締め
和装小物の選び方~帯締め
和装小物の選び方~帯締め
和装小物の選び方~今回は帯締めについてです。帯締めは、帯を固定するのに用いる紐ですが、和装コーディネイトの最後の仕上げの小物ともいえます。
帯締めは、小さなパーツですが、選び方次第で着付け全体の印象も変わってしまうので、着こなしの最後のポイントとなります。
帯締めの歴史は古く、そのルーツである組紐は、奈良時代に唐(中国)の技術に由来します。
一般的に帯締めが使われるようになったのは、江戸時代といわれています。文化年間に人気の歌舞伎役者が、衣裳の着崩れを防止するために、帯の上に締めた紐が用いました。当時の女性がそれを真似て装い、その便利さから“帯締め”として、庶民にも定着しました。
明治の廃刀令の後は、それまで使用されていた丸絎紐はほとんど使われなくなり、刀の下緒に使われていた組紐を、帯締めに用いるようになりました。江戸時代には短かった紐の長さは、次第に長さを持つようになり、今では組紐の帯締めが主流となっています。
帯締めの選び方
帯締めは、帯結びの形を決める重要な役目を果たすもので、帯締めがゆるむと帯全体の形も崩れてしまいます。
帯締めを選ぶときには、絹の弾力性のあるものにすると、よく締まるといわれています。
帯締めは、帯の形を整えるという機能的な面だけでなく、装飾性も兼ねるので、素材や色も選ぶ際の大切なポイントです。
センスに自信のある人は、帯締めもわざと帯と同系色のものを選ぶのもお洒落ですが、そうでなければ、着物や帯の柄の中から、一番少なく使われている濃い色を選ぶと、全体が引き締まるそうです。
帯締めの種類には、丸ぐけ、組紐、打ち紐などがあります。組紐にも、丸組み、平組み、角組みなどがあり、種類も豊富です。
帯締めは、帯の格に合わせて選び、幅も帯の格に合わせます。
留袖には、白の丸ぐけや金、白の格のある組紐などが用いられます。また、水引という、真ん中から金銀に別れているものは、金が本人から見て左側に、銀が右側にくるように締めます。
ミスの礼正装用として、振袖の場合の帯締めは、丸組みの幅が広めのものを選ぶのが一般的です。あまり凝ったものや細めのものは避けるようにし、全体の引き締めるポイントとなる色を選ぶとよいでしょう。
おしゃれ用の帯締めは、柄のあるものや細めの丸組みなど、様々あります。カジュアルな和装の着こなしでは、帯締めもセンスの見せどころですが、帯がゆるまないようなしっかりとした素材のものを選びましょう。
帯締めの主流となっている組紐には、手組と機械組があり、手組のものは”有職組紐 道明 帯締め”など、美術工芸品ともいえるほどの品格を有しており、着物愛好家を魅了しています。
手組の組紐の繊細で乱れを見せぬ美しさは、帯締めとして最高級品と謳われ、組む手法によって、唐組、笹波、貝の口、綾竹、青磁、紅梅、冠(ゆるぎ)、千鳥などと雅な名前がついています。
機械組の帯締めも、近年は研究が重ねられ、正倉院、さざ波、芭蕉など、新鮮な配色のものがつくられ、手組と見分けがつかないほど精巧なものもでてきています。機械組は、手組に比べると、手の出やすい値段で、流行色なども取り入れられています。また、夏用にレースやメッシュ風のものもでてきてバラエティに富んでいます。
近年、若い方やおしゃれ用に、機械組の帯締めを何本も揃えて、気軽に取り替えて、和装コーディネイトを楽しむ人も増えています。